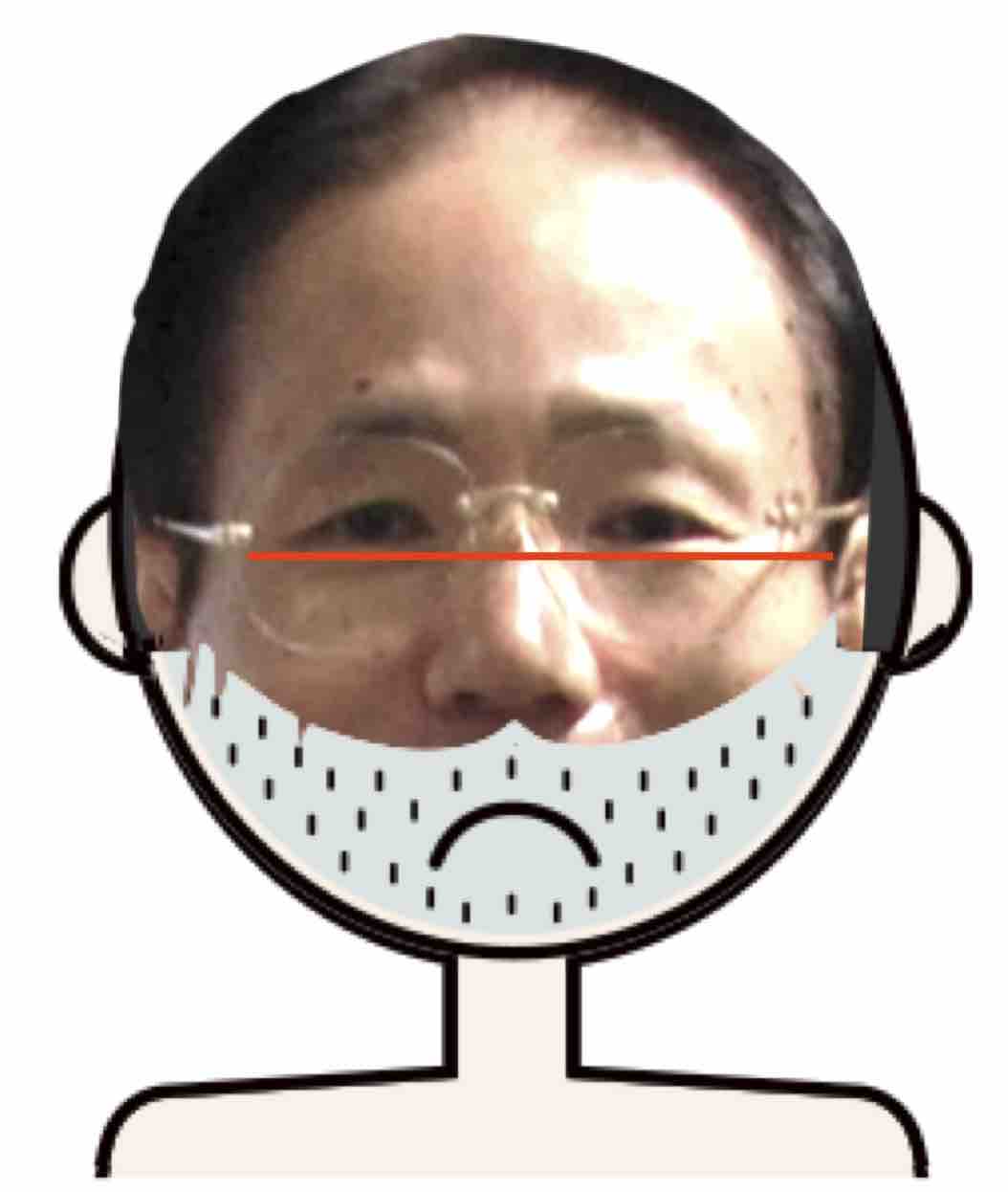「甘い?」
ビエール少年は、頭の中で納豆の味を思い出し、首を捻った。
1967年4月、広島市立牛田中学校1年X組の教室、放課後、英語を教えてもらおうと、数人の女子生徒が、ビエール少年をとり囲んでいた。
「まあ、甘いもんをご飯にかけて食べよっての子もおるんよ」
「ほうなん?」
「従兄弟がねえ、はったい粉に砂糖をまぶしたんをご飯にかけて食べる云うとった」
「はったい粉、なんねえ。それえ?」
「はったい粉、知らんのん?ほうじゃねえ、なんか、きな粉みたいなんよ」
「ああ、きな粉じゃったら、おはぎにも使うけえ、きな粉に砂糖つけてご飯にかけても美味しいんかもしれんねえ。ご飯の代りにおはぎ食べるいうか、お菓子食べるみたいなもんかねえ」
「ウチの弟なんか、砂糖をご飯にかけて食べるんよ」
「え?広島の人て、そんなことするの?」
喧しい女子生徒たちの言葉の交差に入り込む余地のなかったビエール少年が、あまりの衝撃に意図せず言葉を発し、交差の中に入った。
「トンミーくんじゃて、甘いもんご飯にかけて食べるんじゃないねえ」
「え?甘いもんご飯にかけて?」
「醤油も混ぜるんじゃろ?」
「いや、納豆に醤油は混ぜるけど…」
「ほうじゃろお。甘い納豆に醤油かけるん、ウチ、聞いたことないけえ」
「え?甘い納豆?」
ビエール少年は知らなかった。当時(1967年である)、広島で『納豆』といえば『甘納豆』のことであったのだ。『甘納豆』ではない『納豆』を食べる習慣はなく、当時の広島の少年少女たちは、その存在を知らなかったのである。
「まあ、お餅も砂糖醤油で食べるけえ、分からんこともないけど」
「でも、ええ…」
なんでもはっきりものを云う少女『トシエ』が、歯に噛み、小声でそう云った。
(続く)