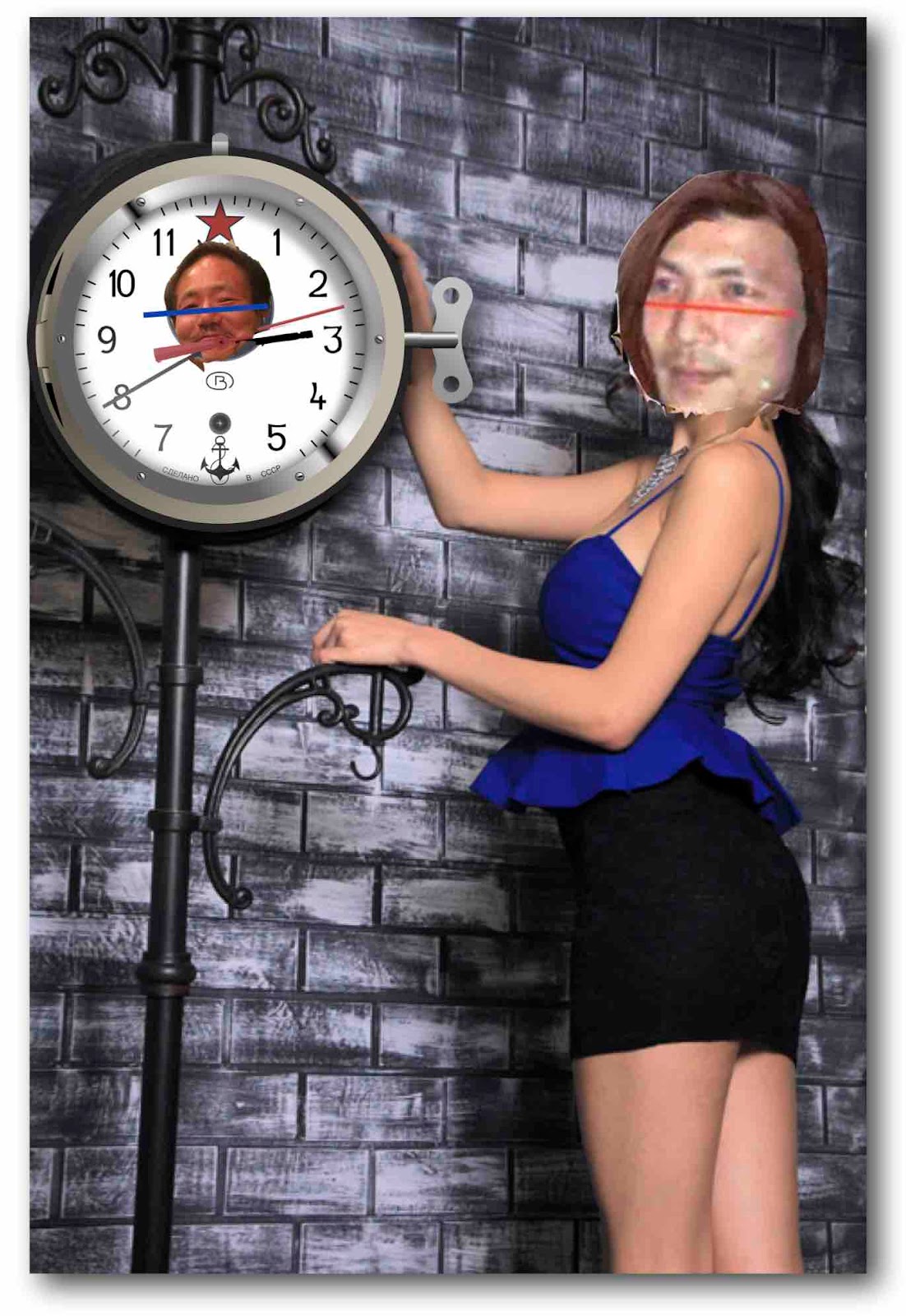「じゃあ、また別の質問をしよう」
と、『少年』の父親は、『少年』に向け、どこか楽しそうに、そう云った。『牛田新町一丁目』のバス停を背にし、家族と共に、自宅へと向っているところであった。
「我々は、『昨日』に行くことができるか?」
「へ?タイムマシンのこと?そんなの本当にあるの?」
八丁堀から牛田まで、随分、時間がかかったような気がする、と『少年』は疑問に思ったのであった。八丁堀から牛田まではバスで10分から15分くらいしかかからないのに、そんな時間ではとてもし切れない程のボリュームの話を父親から聞いたことを訝しく思い、その疑問に対し、『少年』の父親は、『アインシュタイン』の『相対性理論』を持ち出し、時間の進み方が遅かったのかもしれない、と答えた。しかし、『少年』はまだ納得できていないからか、『少年』の父親は、『閏年』があること、更には、『閏年』になるはずの年でも『閏年』にならない年もあることから、『1年』という時間は一定ではないと主張したが、『少年』は、どこか誤魔化されている感を拭えないでいた。そこで、『少年』の父親は、新たな質問を『少年』に投げかけたのであったが、その質問は不可解としか思えないものであった。
「そういえば、まもなく『タイムトンネル』っていうドラマが始まるらしいぞ」
1967年4月8日から、NHKでアメリカのSFテレビ・ドラマ『タイムトンネル』が始まることになっていたのである。
「え?トンネル?」
「見てみないと分からないが、トンネルに入ると未来や過去に行けるらしい。一種のタイムマシンだな」
「でも、ドラマでしょ?」
「そうだな。ドラマだから、タイムマシンだけど、過去にも行けるんだろ」
と、『少年』の父親は、敢えて、そういう云い方をした。
「え?過去じゃなく、未来だったら、本当に行けるの?そんなタイムマシンがあるの?あ、そうかあ、『相対性理論』だね。光の速度に近い速度で宇宙旅行ができるようになったら、未来には行けるんだね。ん、その話はもう聞いたよ」
「おお、もう理解したんだな。いいぞ。そう、『相対性理論』だと、未来にしか行けないな。でも、過去にも行くこともできるんだ」
「ドラマのタイムマシンだったらでしょ?」
「いや、タイムマシンはいらない」
「夢でも見るの?」
「まあ、飛行機か船でもあればいい。場所によっては、クルマでもいいし、歩いてでもいいだろう」
「ああ、光の速度に近い速度の飛行機や船ができたり、人間だって、『エイトマン』のように、ううん、『エイトマン』は『♫弾よりも速く』だから、『エイトマン』よりももっと速く、光くらいの速度で走れるようになったら、っていうことだね。でも、そんなの無理だよ」
漫画『8マン』が1963年から1965年にかけて連載され、テレビ・アニメの『エイトマン』が1963年から1964年にかけて放映されていた。
「いや、光の速度に近い速度で移動できなくてもいい」
と、『少年』の父親は、真顔であった。
(続く)